自律神経の不調に悩まされていませんか?
原因不明の体調不良が長引いたり、風邪を引きやすくなったりして、日常生活に影響するのは辛いですね。
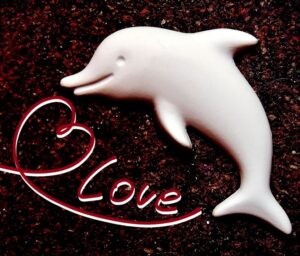
本記事では、自律神経を整える方法や自律神経と関係の深い症状、乱れの原因などについて詳しく解説します。
自律神経による不調が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
自律神経を整えた方がいい?自律神経の乱れが引き起こすこと
自律神経の乱れは、どんな症状を引き起こすのでしょうか?
症状は大きく分けて2つあります。
- 身体的な症状
- 精神的な症状
詳しく説明していきます。
身体的な症状
自律神経の乱れは、身体的な症状を引き起こすことがあります。
身体のあらゆる機能を調整している交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、身体に不調が出やすくなるからです。
たとえば、以下のような症状が挙げられます。
- 肩こり・頭痛
- 手足のしびれ
- 倦怠感や疲労感
- 動悸・不整脈
- めまい・吐き気 など
これらの身体の不調が続く場合は、自律神経の乱れが原因かもしれません。
精神的な症状
自律神経の乱れは、精神的な症状を引き起こすこともあります。
2つの自律神経のバランスが乱れ、交感神経の働きが一方に偏ることが、精神的症状の引き金となるのです。
たとえば、以下のような症状が挙げられます。
- 不安や緊張
- 抑うつ症状
- 過敏性腸症候群
- メニエール病
- 神経性胃炎
- 過呼吸症候群 など
このような不調が続く場合も、自律神経の乱れが関係しているかもしれません。
自律神経が乱れる原因は?
では自律神経が乱れる原因にはどのようなものがあるのでしょうか?
主に以下の6つがあげられます。
- ストレス
- 不規則な生活
- 偏った食生活
- 季節の変わり目の変化
- 病気
- ホルモンバランスの変化
詳しく説明します。
ストレス
ストレスは、自律神経の乱れの主な原因です。
ストレスを受けると、副腎皮質からストレスホルモンのコルチゾールやアドレナリンが分泌され、心拍や血圧を上昇させて交感神経優位の状態を作り出します。
交感神経優位の偏りが、自律神経の乱れへとつながるのです。
不規則な生活
不規則な生活も、自律神経が乱れる原因となります。
不規則な生活をすると、生活習慣が本来の自然なリズムから外れやすくなるためです。
たとえば、夜勤などによる昼夜逆転の生活は、本来自然のリズムで働くはずの交感神経と副交感神経のバランスを逆転させ、自律神経の乱れを引き起こします。
引き金となりやすい睡眠時間の乱れや運動不足などには、特に注意しましょう。
偏った食生活
偏った食生活も自律神経の乱れの原因の一つです。
偏食で栄養の偏りや腸内環境の悪化が起こると、自律神経にも悪影響を及ぼします。
外食への偏りや、寝る前の食べ過ぎ飲みすぎには注意が必要です。
季節の変わり目の変化
季節の変わり目の変化も、自律神経の乱れを引き起こします。
季節の変わり目は気温や気圧、湿度などの変化が大きくなるからです。
たとえば、寒暖差が大きくなると体温調節の機会が増え、自律神経切り替えの機会増加に伴ってバランスが不安定になりがちです。
気温や湿度などの急激な変化に身体が慣れるまでには、自律神経にも負担がかかるのです。
病気
病気の発症を機に、自律神経の乱れが引き起こされることもあります。
他の病状に対する心理的なストレスが重なったり、病気によって生活習慣が変化したりすると、病気とともに併発することも。
また、病気になると気力や体力も消耗しがちで、運動不足にも陥りやすいので注意が必要です。
ホルモンバランスの変化
ホルモンバランスの変化も、自律神経の乱れの原因の一つです。
各臓器と繋がり合う自律神経は、ホルモンバランスの変化に敏感に反応するからです。
たとえば、ストレスや加齢などで女性のホルモンに乱れが生じた場合、子宮・卵巣・脳の中枢神経などの機能調節も共に影響を受けます。
また、ホルモンが乱れる大きな要因には、妊娠・出産による影響や月経などが深く関わっています。
普段から、ストレスが溜まったりホルモンバランスが乱れるような生活環境には注意が必要です。
自律神経を整える方法6選!
では、自律神経を整えるには、どのような方法が効果的なのでしょうか?
主に以下の6つがあげられます。
- 体温調節しやすい服を着る
- 規則正しい生活を送る
- 日光を浴びる
- 首のツボを押す
- お腹のツボを押す
- ストレスを発散する
一つずつ説明します。
体温調節しやすい服を着る
自律神経を整えるためには、体温調節しやすい服を着ることが大切です。
というのも、体温調節しにくい服を着ていると自律神経が酷使され、乱れにつながりやすいからです。
たとえば、朝晩の寒暖差が大きい春先は、着脱しやすい羽織りやブランケットを持ち歩けば、冷えや暑さからくる身体への負担を軽減できます。
衣服やブランケットを活用して、身体の体温調節を助けることで、自律神経のバランスを保ちやすくなります。
規則正しい生活を送る
規則正しい生活を送ることで、自律神経が乱れにくくなります。
自律神経は生活のリズムの乱れに呼応して、乱れやすくなる傾向があるからです。
日中によく身体を動かし、夜はしっかり休息をとるなど、リズムの整った生活を送ることで、自律神経は整います。
自律神経の切り替えがしっかりと機能するような生活習慣を身につけることが大切です。
日光を浴びる
自律神経を整えるためには、日光をしっかり浴びることも大切です。
日光を浴びることで、脳ではセロトニンの分泌が盛んになり、体内時計が整うからです。
体内時計が整うと、日中にしっかりと交感神経の覚醒スイッチが入り、夜は副交感神経の弛緩スイッチに切り替えるリズムがスムーズになります。
朝起きたらすぐに、太陽の光を浴びる習慣を持つといいですね。
首のツボを押す
首のツボを押すことも、自律神経の乱れを整えるのに効果的です。
首には、自律神経の乱れを整えるのに効果的なツボがあります。
特に、自律神経の乱れによりコリや停滞が起こりやすい、首の裏や後頭部の血流を促すとよいでしょう。
自律神経を整えるのに有効なツボを、以下に3つ紹介します。
- 瘂門(あもん):
後頭部中央、髪の生え際から指1本分ほど上 - 風池(ふうち):
首付け根の筋肉の盛り上がりより、左右に1cmほど外側のくぼみ - 天柱(てんちゅう):
風池から親指1本分内側から、1cmほど下
それぞれのツボは、ゆっくりと圧を強めながら押し揉んでいくのがポイントです。
お腹のツボを押す
お腹のツボを押すことでも自律神経が整います。
お腹のツボ押しは内臓の血流を促し、ストレスで優位になりやすい交感神経の働きを静めるとともに、副交感神経の働きを高めてくれるからです。
自律神経を整えるのに有効なお腹のツボを、以下に3つ紹介します。
- 中脘(ちゅうかん) へそとみぞおちを繋ぐ真ん中
- 天枢(てんすう) へその左右、指3本分
- 関元(かんげん) へその下に指4本分
どのツボも「若干痛いが、気持ちいい」と感じる程度に指を入れて、揉みほぐしてみてください。
ストレスを発散する
適度にストレスを発散することも、自律神経を整えるのに有効です。
自律神経は、ストレスによって傾きやすい傾向があるからです。
普段から定期的に散歩したり、腹から声を出して歌ったりお風呂上がりにストレッチするなど、ストレスを溜めにくい体質づくりが大切になります。
ストレス発散には、身体も心もすっきりリフレッシュでき、かつ温まるようなものがおすすめ。
そうした動きを日常に取り入れるだけで、ストレスで弱まりがちな副交感神経の働きは高まりやすくなります。
まとめ
自律神経を味方につけ元気に生活するためには、乱れの原因を知り、できるだけ要因となるストレス刺激を避けることが大切です。
本記事では、自律神経を整える方法や関係の深い症状、乱れの原因などについて詳しく解説してきました。
自律神経による不調が気になる方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。


コメントを残す